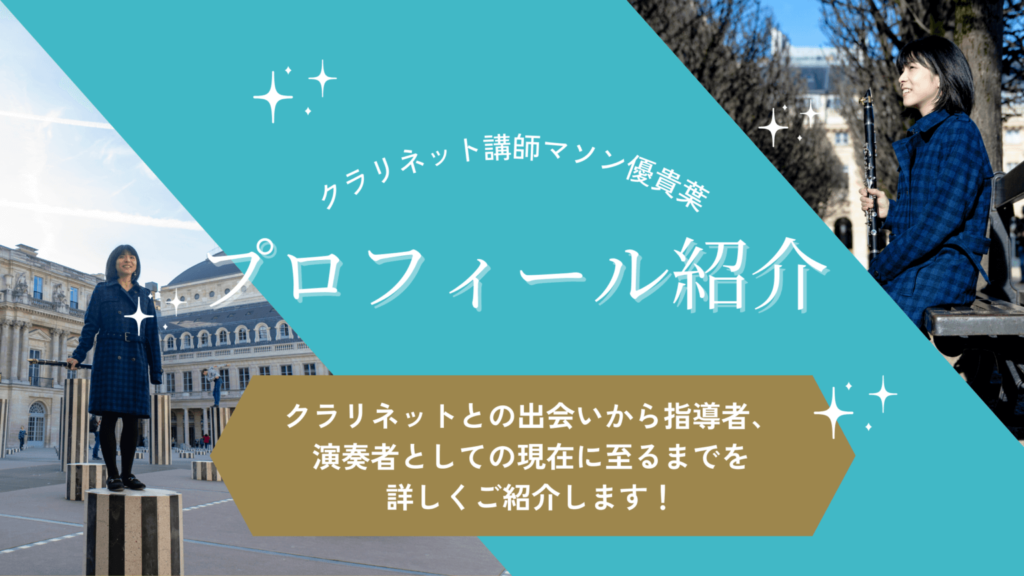楽譜の書き込みってどうしたらいいの?素早く、わかりやすい書き込みのコツをご紹介

ソロや吹奏楽、オーケストラなどなどで演奏するとき、先生に言われたことや、自分で注意したいことなど、楽譜に色々と書き込みをすることがあるかと思います。
書き込みをするときに、できるだけ素早く、わかりやすく書き込むことができれば、スムーズに練習が進み、色んなことに注意しながら演奏しやすいと思います。
ということで今回は、楽譜に書き込みをするコツを書いてみたいと思います!
- 吹奏楽やオーケストラをやっている方
- 楽譜の書き込みの仕方がよくわからない方
- 楽譜の素早い書き込みのコツを知りたい方
メモすることは大切!

曲を練習していて、指揮者や先生、先輩などからアドバイスを受けたり、自分で気をつけたいと思ったことなどがあれば、すぐに楽譜に書き込むことが大切です。
せっかく教えてもらったことを忘れてしまったり、いざというときに注意してできなければ、いつまで経っても治すことができず、上達への道は遠くなってしまいます、、
なので、気をつけることは忘れないうちに、楽譜のあいているところに、ささっとメモしておきましょう!
素早くわかりやすく書き込む

合奏の合間やレッスン中などの限られた時間だと、書き込みはなるべく素早く書くことが大切になってきます。
もちろん、丁寧に書くことも大切ですが、書くことばかりに時間を取られてしまっては、せっかくの練習時間が勿体ないですよね?
 マソン優貴葉
マソン優貴葉文字の代わりに、簡単な記号や印などを使うのも素早く書き込むコツです!
そして、書き込んだことを後で見てもすぐに理解して、演奏に活かせるように、わかりやすく書くことも大切!
時々、後で自分で書いたものを見て、何を書いたのかわからなくなってしまっている方もいるので、せめて自分だけにはわかるようにしておくと良いですね!
 マソン優貴葉
マソン優貴葉楽譜の書き込みは、練習を重ねるうちにだんだんと増えていくかと思いますが、特に気をつけたいことは、ぱっと見てわかるようにしておくと良いですね。
書き込みの例

ということで、わたしが普段使っている、書き込み方法をご紹介します!
 マソン優貴葉
マソン優貴葉色々な書き込み方法があるので、自分がわかりやすいと思う書き方で全然良いのですが、一例として、参考になれば嬉しいです。
1. 速度に関すること
遅くする

「ritardando(rit.)」のように、テンポをここで緩めたい!というところには、波線を書いています。
だんだん速く

「accelerando(accel.)」のように、だんだんテンポを速くしたいところには、ぐるんとした矢印を書いています。
前へ

どうしても無意識にテンポが落ちてしまうところや、前へ進みたいときには、「右矢印(→)」を書いています。
慌てない

無意識に慌ててしまったり滑ってしまったりと、テンポが速くなってしまうところには、「左矢印(←)」を書いて、後ろへ引っ張られるような意識で演奏するようにしています。
2. 強弱

例えば、「大きな音で演奏して!」と言われたら、「f」を書いたり、小さな音で演奏したいときは、「p」を書いたりと、楽譜に書いてある強弱とは別で、自分にわかりやすく大げさな強弱記号を書いています。
3. フレーズの頂点

旋律を演奏するときに、フレーズの持って行き方のアドバイスを受けることがあります。
そんなときは、フレーズが向かった先の頂点 (フレーズが一番盛り上がる部分) に「^」を書いておくと、パッと見てわかりやすく演奏しやすいです!
4 . 区切る

フレーズを区切りたいところや、いったん音楽を止めたいところなどには、「/」を書いています。
5. リズムをわかりやすくする

ときには、ちょっと複雑なリズムが登場することもあり、楽譜が読みにくいこともあります。
そんなときは、音符の上に拍ごとに線を書いて、何拍目に音があるのかや、音を出すのは表拍なのか裏拍なのかを明確にしたりしています。
6. 指揮者に関すること
指揮をよく見てマーク


指揮者がテンポを急に変える場所や、指揮者にしっかりと合わせて音を出したいときなど、指揮者をよく見て!という意味で、「メガネ」や「目」を書きます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉わかりやすくてインパクトがあるので、自然と指揮を見てしまうと思います!
指揮者が何拍子で振るか

曲の中では時に、同じ拍子でも、指揮者が1小節をいくつに分けて振るのか、急に変わったりすることがあります。
例えば、1小節を2つで振るのなら「in 2」と書いたり、6つに分けて振るのなら「in 6」と書いて、いくつ振りかをメモしておくと、指揮がさらにわかりやすくなると思います。
7. よく聞きたい楽器の名前

色んな楽器と一緒に演奏する合奏の場合は、「ここは、この楽器としっかり合わせたい」や「ここはこの楽器の音をよく聞いて演奏したい」など、ところどころで、特定の楽器をよく聞きたいということが出てくるかと思います。
そんなときは、楽器の名前をメモしておくだけで、そちらに耳が傾きやすくなります。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉楽器の名前は、「Fl」「Tp」など、できるだけ省略系を使うと素早く書くことができます♪
8. 奏法に関すること
息継ぎの場所

息継ぎをどこでするかは、V字でブレスマークを書いています。
逆に、ここで息継ぎをしてはいけないという場所には、V字の上に×を書いています。
使う指の左右

例えばクラリネットの場合は、小指のキィを左右どちらで押すのかというのがあるのですが、複雑で忘れそうなときに、わたしの場合は右を「R」、左を「L」と、音符の下にメモしています。
まとめ
楽譜の書き込みの仕方次第で、自分だけのわかりやすい楽譜が完成します。
素早く書き込むのは、最初はなかなか難しいかもしれませんが、慣れていけば、素早くきれいに書けるようになると思うので、是非、色んな方法を試して、自分に合った方法を見つけてみてください!
楽器練習アプリの紹介
クラリネットの練習には、ゲーム感覚で楽しく楽器練習ができちゃうアプリもおススメです♪
7日間の無料トライアルもあるので、良かったら試してみてください!

\7日間の無料トライアルあり/