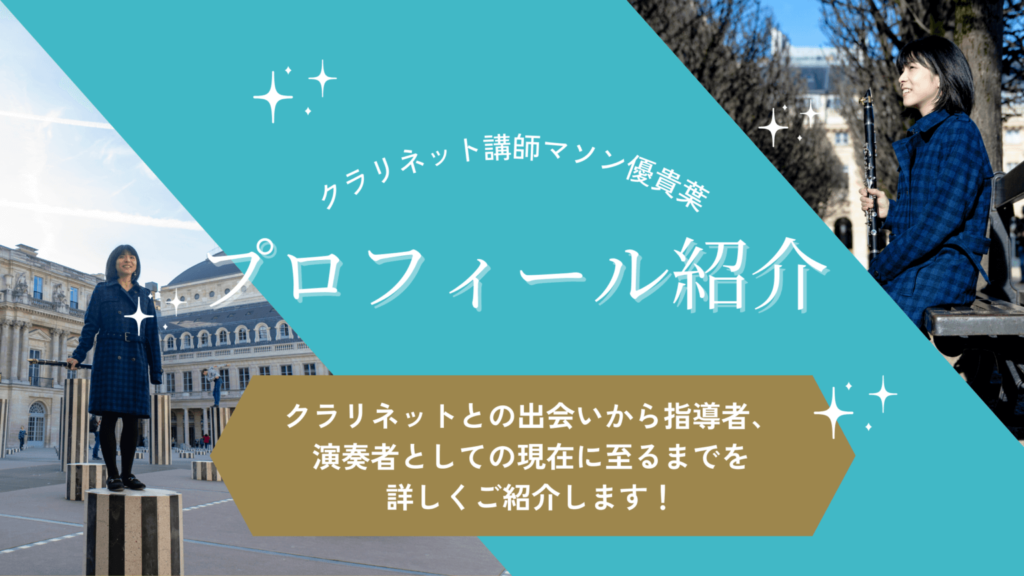部活動にクラリネットの新入部員が入ったらどうする??後輩へ教え方をご紹介します!

部活動では、学年が上がると、かわいい後輩たちが入部してきます☆
先輩になると、後輩にクラリネットを教えることがあると思います。
教え方によっては、後輩たちをうまく育てることもでき、後輩たちからかっこいい先輩として尊敬されたり、感謝されちゃったりするかもしれません。
そしてその後輩たちがまた新しい後輩を育て、、
とどんどんつながることで、部活動全体のレベルもどんどん上がっていきます。
でも、何からどうやって教えたらいいの??と困ってしまうこともあるかと思います。
ということで今回は、クラリネットの後輩の教え方を1から書いていきたいと思います!
- これから後輩が部活動に入ってくる方
- 部活動で後輩にクラリネットを教える機会がある方
- 後輩の教え方に悩んでいる方
まずは楽器の扱い方から!

まず最初に後輩に伝えてほしいことは、“クラリネットは繊細“だということ!
丁寧に扱わないと、すぐに壊れてしまうということをしっかり理解してもらいましょう。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉楽器は安いものではないですし、せっかく練習しようとしても壊れていてはなにもできませんしね!
クラリネットに良くないことは、こちらの記事に書いてあります!

それを理解してもらったら、早速クラリネットの組み立て方を教えていきます♪
楽器の組み立て方も、しっかり教えておかないと、楽器が故障する原因にもなってしまいます、、
組み立て方はこちらの記事をご覧ください♪

そして、クラリネットの置き方も忘れずに教えましょう!
時々、楽器の置き方を知らない学生さんを見かけることもあり、見ていてヒヤッとする場面に出くわすこともあります。
楽器の置き方はこちらの記事をご覧ください!

 マソン優貴葉
マソン優貴葉取り扱い方によっては楽器に良くない影響を与えてしまうことにもなりかねないので、ここは手を抜かず、1つ1つ丁寧に教えるようにしましょう☆
リードのつけ方を教えよう!

楽器の組み立てができたら、クラリネットにとってとても大切な「リード」のことを教えてあげましょう!
リードはとても繊細で、むやみに先端に触れるとすぐに割れてしまうことや、割れたら使えなくなってしまうことを伝えます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉1本あたりの大体のお値段を言っておくと、大切に扱うようになるのかなと思います笑
そして、リードはバラ売りでなく、箱で買う方が良いこと、何枚かをローテーションで使うのが良いことなども教えておくと良いですね!
リードの扱い方はこちらの記事をご覧ください!

そして、リードを湿らせたら、「リガチャー」を使ってリードをマウスピースに固定します。
リードのつけ方は最初は難しいと思うので、こまめに先輩がチェックしてあげるようにします。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉時々、リガチャーを反対向きに付けている学生さんを見かけるので、基本は「自分から見て右側にネジがくるように」と教えてあげると良いですね!
リガチャーのつけ方はこちらの記事をご覧ください!

構え方を教えよう!

組み立てができたら、楽器の構え方を教えましょう!
両足を肩幅に開き、肩に力が入らないようにリラックスした状態で、右手親指の関節あたりに指掛けがくるようにして、クラリネットを持ってもらいます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉楽器の重さが右手の親指にかかるので、最初はなかなか楽器を持つのだけでも大変で不安に思ってしまう子もいるかもしれませんが、「慣れたら大丈夫だよ!」と言って後輩を安心させてあげることも大切なポイントです☆
そして、どのトーンホール(穴)をどの指でふさぐのかを説明します。
「指の真ん中の膨らんだ部分がトーンホールの真ん中くらいにくるように」と教えてあげると良いかと思います♪
キィもそれぞれをどの指で押さえるのかも一応説明しても良いかと思いますが、キィはたくさんついているので、いきなり全てを覚えるのは難しいかもしれません。
運指を覚えながら、少しずつ教えていきましょう!
音の出し方を教えよう!

さて、ここからいよいよ音を出してもらいます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉クラリネットを初めて吹く後輩は、ドキドキワクワクの瞬間なので、温かく見守ってあげましょう♪
まずはアンブシュアの作り方を教えてあげます。
アンブシュアは人それぞれ色んな表現の仕方があると思いますが、わたしがアンブシュアを教えるときのやり方をご紹介します♪
という感じで、アンブシュアの形を教えています。
アンブシュアは、普段はなかなかしないような口の形なので、慣れるまでは苦労するかもしれませんが、あまり神経質にならず、力まずに自然な口の形を大事にしてあげると良いですね!
それができたら、楽器に息を入れて音鳴らします。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉まずは開放のソの音から始めると良いと思いますが、楽器が安定しなくて吹きにくい場合は、他の音でも良いです♪
なかなか息が入らずに音が出ないときは、最初はマウスピースとバレルだけで音の出る感覚を掴むというのもありだと思います。
とにかく、何でも良いので音を出してもらって、音を出す楽しさを知ってもらいましょう!
運指を教えよう!

ある程度音が鳴るようになったら、運指を教えていきます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉クラリネットの運指表を準備して渡しておくと良いですね!
クラリネットは、穴をちゃんとふさがないと音が出ない楽器なので、ふさぐ穴の数が少ない音から順番に鳴らす練習をしていくと良いと思います。
最初は開放のソから、ファミレド…と、順番に降りてきます。
一番低い音のミまで鳴るようになったら、それを出しながらレジスターキーを押してもらって、シの音を出す練習をします。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉クラリネット初心者さんにとって「シ」の音はとても難しい音なので、出なくても落ち込まないように、励ましながらやっていきましょう!
「シ」の音を鳴らすコツはこちらの記事をご覧ください!

定期的にやる基礎練習を教えよう!

音がある程度出るようになって、運指も覚えてきたら、基礎練習のやり方を教えてあげます。
基礎練習は毎回の練習の前にやる、とても大切な習慣です。
部活動で決まったものがあれば、それを丁寧に教えてあげます。
基本的にはロングトーン、音階、タンギング辺りをやっておけば良いかと思います。
できれば、オクターブ練習もやってみましょう♪
いくつか楽譜を載せておきますので、良かったら使ってください(o^―^o)
曲の練習方法を教えよう!

基礎練習のやり方までマスターしたら、楽譜をわたして曲の練習をやっていきます。
部活動でクラリネットをやっている子の中でも、ピアノなどの楽器を習っていて楽譜がしっかり読める子もいれば、音楽の教科書以外では楽譜なんて見たことのないような子もいます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉楽譜が読めない子には、まずは音の高さやリズムの読み方などから、丁寧に教えていきます。
どんなことができてどんなことができないのか、まずは後輩たちそれぞれのレベルを確認してから話を進めていくことが大切です。
そして、曲を練習するときに大切なことは、できないところを速いテンポでやりすぎないことです!
楽譜に書いてある速さで演奏することはもちろん大事なことですが、練習の段階では確実にできる速さからやっていきます。
そして、練習には必ず「メトロノーム」を使います。
メトロノームをゆっくりから始めて、少しずつテンポを上げていって、最終的に書いてある速さで吹けるようにします。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉できないのに速いテンポでばかり練習していると、悪い癖がついてしまって、せっかくの練習も逆効果になってしまうので気をつけましょう!
こんな感じで練習の仕方を教えながら、後輩がわからないところも聞きながら進めていきましょう!
楽器の片付け方までしっかり教えよう!

クラリネットの練習が終わるときには、片付け方もしっかり教えてあげましょう!
クラリネットは特に水分に弱く、水分が楽器についたままだと、楽器が割れてしまう恐れがあるので、しっかりと水分を拭き取るようにすることを伝えます。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉リードの片付け方まで忘れずに細かく教えてあげましょう!

片付けができたら、楽器ケースの置き方も教えておきます。
楽器ケースは表が上になるように、もしくは立てて置くようにします。
 マソン優貴葉
マソン優貴葉裏面を下にしてしまうと、キィが曲がったり、調整がずれたりしてしまうことがあるので注意しましょう。
まとめ

後輩を教えてあげるのは大変なことかもしれませんが、自分が最初に先輩から教わったことを思い出しながら丁寧に教えてあげれば、きっと後輩もそれに答えてくれると思います。
そして、後輩を教えることで初めて気づくこと、自分が学ぶこともたくさんあります。
後輩たちと一緒に、みんなで素敵な部活動を作っていけると良いですよね☆
楽器練習アプリの紹介
クラリネットの練習には、ゲーム感覚で楽しく楽器練習ができちゃうアプリもおススメです♪
7日間の無料トライアルもあるので、良かったら試してみてください!

\7日間の無料トライアルあり/